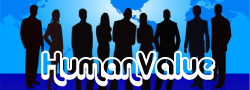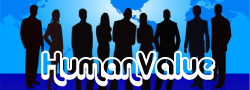第一章 キャッシュフロー経営とはどういうものか
第四節 儲けの形が変化するキャッシュフロー
ここでは、「儲けの形が変化する」という題で、キャッシュフローのもう一つの要素についてお話をします。
| 項 目 |
金 額 |
| 売上高 |
500 |
| 売上原価 |
350 |
| 売上総利益 |
150 |
| 販売費及び一般管理費 |
100 |
| 営業利益 |
50 |
| 受取利息 |
1 |
| 支払利息 |
2 |
| 経常利益 |
49 |
| 税金 |
20 |
| 当期利益 |
29 |
その前に、再度企業の利益構造について確認をします。先ず右の図表をご覧下さい。
売上総利益は売上から売上原価を差し引いたものです。
営業利益は売上総利益から一般管理費を差し引いたものです。
経常利益は営業利益に受取利息を足し、支払利息を引いたものです。
最後に当期利益は経常利益から税金を差し引いたものです。
ここまでは大丈夫でしょうか。ここで、未だよくという方は、会社の会計構造を知るの項を参考にしてみてください。
では、以上を理解できた(会社損益の構造)、ということで、
その中でもなかなか解りにくい売上原価をもう少し詳しく見てみましょう。
以下の図表は売上原価の体系を示したものです。
|
昨日までの在庫
|
200
|
|
今日売れた在庫
+
今日仕入れた
在庫で販売分
=
売上原価
|
|
|
今日の仕入
|
|
|
|
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
|
今日の残り
|
300
|
|
200+2000-300=1900
|
細かくするともっと複雑なのですが(特に製造業などにおいては・・・)、ここでは、一般的な見方をします。
なにやら難しそうな表ですが、解説をお聞きください。
一般的に商売を始めた日或いは毎日売り切りのお店は別として、多くの場合、最初は前日の売れ残り(在庫分)からスタートします。
前日の売れ残り(在庫)をさばくだけでは目標の売上が達成できない場合は、本日売る分を仕入れなければなりません。
それが、ここにある今日の仕入れです。
上記の図では、前日の残り200円と今日の仕入2000円が今日売れる可能性のある商品ということになります。
夕方になりお店を閉めたところ300円分が売れ残ってしまいました。ということは、
今日売れた商品の原価(元値)は前日の200円に当日の2000円を足し、残った300円を引くことで求めることが出来ます。
これに従えば今日の売上原価は1900円ということになります。(200+2000-300)
もし売値を元値の2割増で販売しているとすれば2280円ということになります。しかし、実際にこの売上金がレジないとすれば、万引きやレジ打ちミスなどが考えられます。それはさておき、売上原価とは、売上に応じて発生するということがお解かりいただけましたでしょうか。
この解説をさらに詳しく見てみます。では、売上原価と資金収支という視点で見てもらいます。先ず以下の表を見てみて下さい。
|
項目
|
金額
|
|
入金
|
出金
|
残高
|
|
月初め在庫
|
500,000
|
|
|
|
5,000,000
|
|
当月仕入
|
3,000,000
|
|
|
3,000,000
|
2,000,000
|
|
月末在庫
|
800,000
|
|
|
|
2,000,000
|
|
売上原価
|
2,700,000
|
|
|
|
2,000,000
|
|
利益率
|
20.00%
|
|
|
|
2,000,000
|
|
売上
|
3,375,000
|
|
3,375,000
|
|
5,375,000
|
|
原価
|
2,700,000
|
|
|
|
|
|
利益
|
675,000
|
|
|
|
|
今度は一ヶ月間で見ていますので、「月初めの在庫」と記してあります月初在庫は50万円です。
今月の仕入高は300万円、月末の在庫は80万円とありますので、先程の算式に従えば(50+300-80)、270万円が原価ということになります。
これに20%の利益を付して販売したとすれば売上高は3375万円となります。
売上総利益を求める算式は売上高から売上原価を差引けばよいのでここでは67.5万円となります。
上図右側の実際資金の動きを見て下さい。
ここでは前月よりの繰越として現金が500万円あったと仮定してスタートしています。まず、300万円の仕入資金が支出されています。
次に337.5万円の入金があります。残高は537.5万円で37.5万円の現金増となっております。
この数字は利益の67.5万円と食い違っています。
これが第三の視点、利益が形を変えるというものです。
さらにこれに前述の租税負担分を仮に利益に対して40%あったとすると、67.5万円×40%で27万円となり、、最終の現金残が10.5万円となります。
|
項目
|
金額
|
|
入金
|
出金
|
残高
|
|
月初め在庫
|
500,000
|
|
|
|
5,000,000
|
|
当月仕入
|
3,000,000
|
|
|
3,000,000
|
2,000,000
|
|
月末在庫
|
800,000
|
|
|
|
2,000,000
|
|
売上原価
|
2,700,000
|
|
|
|
2,000,000
|
|
利益率
|
20.00%
|
|
|
|
2,000,000
|
|
売上
|
3,375,000
|
|
3,375,000
|
|
5,375,000
|
|
原価
|
2,700,000
|
|
|
|
|
|
利益
|
675,000
|
|
※5、000、0000+675,000=5,675,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税金
|
270,000
|
|
実質手許現金
|
5,105,000
|
これは、前述の経費ではない支出と異なり確かに原価(仕入)という経費ではあるのですが、それは、売れた時に経費(仕入)として認めますよという観点のものです。
だから、実際に仕入れとしてお金を払ったとしても無駄骨(経費としてはみてもらえない)になるということです。
しかし、中小企業の経営者はよくこれをやりたがります。この設例でも増えた30万円の在庫は次に売るための商品ですので別に問題視することも無いのですが増えた在庫分がもう売れそうにない死蔵品(デットストック)を賄う形で増えたものだとしたら、その利益は実質なかったものとして扱われなければいけません。
しかし、なかなかそのように扱われないのも事実です。このことをよく知らずに決算期に入り、やたら材料を購入し経費にしようとしたところ、税務調査で否認され追徴課税を強いられたという話はよく聞きます。
また、利益分はデットストックということもあります。
M社は毎年利益を出してはいるのですが、それと同等に近いくらいの在庫が増え続けていました。売上のボリュームが大きくなり、在庫が増えていくのはなんとなく理解できるのですが、M社は売上の増加は微増で在庫が増えるという不自然な状態が続いていました。
実際に調査したところ、在庫の約半分は死蔵品(デットストック)であったという事実が明確になりました。
これは売れる可能性の全く無い商品によって租税負担が増加してしまうのです。仕入れの失敗や、世の中の目まぐるしい流れの中で商品が陳腐化するというのはよくあることです。
実際、店頭在庫をきちんと調査したところ、3年間に亘って全く売れていないという商品が売り場を占有していたという例もあります。
この会社では、商品の仕入れや選定をそのお店の店長に任せていました。店長は、会社側から売上を増すように指示されているため、売れそうな商品を仕入れます。
その一方で見込み違いの商品が店頭に並ぶことになり、経営者は売上が増えたと喜んでいるのですが、先程の例により、増えた売上と利益とは、形を売れない在庫という形に変化をし、お金も足りない状況を作り出していたという訳です。
お金がまわっているのでその重要性についてあまり考えませんが、いざ回らなくなったときに、この行動が資金繰りの失敗を招いてしまう要素となることも事実です
|
|